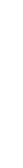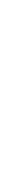Defect 抜歯となった後の欠損治療について

虫歯や歯周病で歯が欠損してしまうと、以前のように良好に噛めないだけでなく、様々な体の不調を引き起こす場合もあります。そこで、早急に欠損部分を補う必要があります。
抜歯後の歯の代わりとして、そして患者様の残った歯を守る方法として、インプラントはお勧めの治療法です。入れ歯やブリッジと比較して、患者様の残った歯を失うリスクが最も低い治療法だからです。さらに、インプラントは「第二の永久歯」と称され、耐用年数が長いことでも知られています。定期的なメインテナンスの実施によって、天然歯と同様に長く使い続けることが可能です。
残存歯が20本以下になると、認知症や転倒などのリスクが上昇すると言われています。将来、元気で長生きするためにも、残存歯を重視した治療を一緒に考えていきませんか。
欠損歯を放置するリスク
歯を抜けたまま放置すると虫歯や歯周病になるだけではなく、歯の移動がおこり、噛み合わせが崩壊します。 噛み合わせの崩壊は顎関節症や肩こりなど全身の病気を引き起こします。 早めに適切な治療を受けてください。
RISK
歯を抜けたまま
放置するのは危険です
-
RISK 
顎全体のズレにつながる
歯が抜けた後にそのままにしていると、抜けた歯の対側の噛み合うべき歯がその空いたスペースの方向に伸展してゆきます。どんどん伸びてきて、欠損歯の隣りの歯に当たり、干渉し合うようになると、顎全体がずれていきます。
また、対側の歯が伸びた後で治療を開始すると、スペース確保のために、伸びてきた歯を削り短くする必要が出てきます。状態によっては歯を大きく削ることもあります。 -
RISK 
その後の治療が複雑になる
欠損歯と隣り合う歯が、歯が抜けて空いたスペースに移動してきます。つまり、歯が斜めに倒れたような状態になりますが、倒れた歯の根元部分には汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病が発生しやすくなります。次に、奥の歯が倒れてくるなど、かみ合わせが徐々に崩壊し始めます。
また、いざ治療を受けようとなった段階で、治療が複雑になってくるのです。例えば、ブリッジ治療では歯を細く削る必要が出てきます。伸びた歯の傾斜がきつい場合は根管治療を行う必要も生じ、治療は長期を要します。インプラントや入れ歯の場合も、隙間が狭いので前後の歯を削る必要が出てきます。 -
RISK 
顔貌の老化が進んでしまう
経験しないとわからないものですが、歯が抜けると、お顔の印象がぐっと悪くなります。原因は、歯の抜けた部分の歯槽骨が下がり、歯ぐきが下がるため、どうしても衰えた印象を与えてしまうからです。さらに、奥歯を失ったお顔は、頬がこけてしまったり、頬が中心部に寄ってきたり、顎がゆるみ、全体的にたるんで見えたりと、顔貌の老化が著しくなる場合が多いのです。
-
RISK 
発音や食生活に支障が出る
歯を抜けたままにしても、即時の支障はないのですが、やがて食事や発音などの機能面に大きな支障が現れます。さらに、全身的な病気のリスクが増加し、生活の質が低下します。
例えば、食生活ですが、食べられる(噛める)食材というのは歯の本数で決まってくるのです。抜けた歯を放置して、口内を崩壊させて行くと、食の楽しみばかりか摂取できる栄養素もどんどん乏しくなってしまいます。また、発音しづらくてコミュニケーションに支障が出てくると、家にこもりがちになり、精神的にも脆弱化します。認知症リスクも上がると言われています。
インプラントと入れ歯の
違い
インプラントと入れ歯の決定的な違いは人工歯根の有無です。インプラントは外科手術を行って人工歯根を顎の骨を埋め込み、人工歯を装着して噛む機能を回復させます。入れ歯は人工歯根を用いず、歯を失った部分に取り外し式の義歯をはめます。失った歯の機能を回復させるには、最もオーソドックスな治療法が入れ歯です。しかしインプラントと比較すると、どうしても噛む力や噛み合わせに問題が生じやすくなってしまいます。
-

インプラント
インプラントとは、人工の材料や部品を体に入れることの総称で、歯科では歯を失った顎の骨(顎骨)に体になじみやすい材料(生体材料)で作られた歯根の一部あるいは全部を埋め込み、それを土台にセラミックなどで作った人工歯を取り付けたもので、一般には口腔インプラントあるいは歯科インプラント、または、単にインプラントと呼ばれています。人工的な歯根を植え込み、歯を取り付けるので、見た目も使用感にも優れ、自分の歯と同じようにしっかりと噛めます。
-

入れ歯
部分入れ歯の場合、歯の欠損部の両サイドや反対側の残った自分の歯に「クラスプ」と呼ばれる入れ歯維持用のバネをかけ、部分入れ歯を維持します。「床」と呼ばれるピンクの樹脂でできた部分が欠損部の歯ぐきに接するため、何となく違和感や異物感を訴える方が多いようです。加えてバネのかかった歯は清掃性が悪くなり、負担も受けやすくグラつきやすくなります。また、安定して噛む事が難しい、うまく発音できない、見た目がよくないなどの問題があります。
インプラント治療の
メリット・デメリット
インプラントのメリット
- 審美性、機能性にとても優れている
- 天然歯に近い自然な噛み心地
- 他の歯に影響を与えず
治療することができる - 対合の歯に負担があまりかからない
- 顎の骨の吸収を抑制できる
インプラントのデメリット
- 外科手術を伴うため、
誰でも
治療ができるわけではない - 保険適用外のため、
高額な治療費が必要になる - 治療期間が長くなり、人工歯を
装着するまで
不便を感じる
このように機能面や審美性などの面ではインプラントが大変優れています。また他の歯の健康を守るという観点で考えても、インプラントは優れています。しかしインプラントは保険適用外で高額というだけでなく、手術を要するため、誰でも適しているわけではありません。
入れ歯は機能面や審美性、そして噛む力に劣ります。しかし保険適用で安価に作製できること、そして治療期間が短い点でインプラントよりも優れています。 どちらがご自身に適しているのかを考え、歯科医師とよく相談して治療方法を選ぶことが大切です。
OVERVIEW

当院のインプラント治療について

当院では、**抜歯即時埋入(Immediate Implant Placement)**を積極的に導入しています。
この手法は、抜歯と同時にインプラント体を埋入する高度な術式であり、条件が整えば従来よりも短期間・低侵襲での治療が可能です。
治療概要
抜歯即時インプラント
当院では術前にCBCT(歯科用CT)を用いた三次元的な骨評価を行い、埋入位置や埋入角度を正確に計画します。
| インプラント埋入時期 | 抜歯当日 |
|---|---|
| 治療期間の目安 | 約3ヶ月(症例により異なります) |
| 使用するインプラント体 | 抜歯した抜歯窩を上手く利用するため直径の太いインプラントのメガジェン社のインプラントを用いています。 |
臨床的メリット
-
治療期間の大幅な短縮
通常6~8ヶ月を要するインプラント治療が、即時埋入により約3ヶ月で補綴まで完了可能です。
当院では6週目でISQを測定し十分な固定を確認したら8週目で型取りを行い10週目で最終補綴をセットします。
(上顎臼歯部など垂直骨量が少ない場合はもう少し治療期間が伸びますがそれでも 3~4ヶ月で終えることができます。) - 歯槽骨の温存 抜歯後の骨吸収を抑え、審美性・機能性の維持に有利です。特に前歯部では歯肉ラインの保持にも寄与します。
- 手術回数の低減 抜歯と同時に埋入することで外科的処置が1回で済み、患者様の身体的・心理的負担も軽減します。
-
審美補綴への応用性
前歯部症例では、必要に応じて**即時暫間補綴(仮歯の即時装着)**にも対応し、審美的・機能的 ニーズに配慮します。
(前歯以外でも十分な初期固定が取れれば仮歯を作成します)
適応と限界

抜歯即時埋入は、十分な初期固定が得られること、軟組織の安定性が予測できることが成功の伴です。感染の存在、骨欠損の大きい症例、高度の喫煙者などでは適応外となることがあります。適応症の選定には、的確な診査・診断が不可欠です。

インプラント治療は「埋めるだけ」ではありません
のうが歯科医院では、林 揚春先生によって提唱された「4Sコンセプト」に基づき、患者さんの安全・安心・満足を第一に考えたインプラント治療を行っています。多くの方が「インプラントは失った歯の代わりに人工歯根を骨にただ埋めるもの」と認識されていますが、実はその“埋入位置”が治療の成否を大きく左右します。
たとえば──
- 垂直的な埋入深度が不適切だと、最終的なかぶせ物(上部構造)の形に影響し、清掃がしにくくなることで将来的な炎症リスクが高まる可能性があります。
- 埋入角度がわずかにずれるだけでも、見た目の自然さ(審美性)や噛み合わせ、長期的な安定性に問題が生じることがあります。

日常生活では、数ミリのズレやわずかな角度の違いを気にする場面はあまりないかもしれません。しかし、インプラント治療においては、その“わずかなズレ”が治療結果に大きな影響を与えることがあります。
こうした理由から、当院では治療前の診査診断を徹底し、CTや3Dシミュレーションを用いて最も適切な位置・角度・深さでの埋入計画を立てています。
どのインプラントシステムを使うか以上に、「治療前にいかに計画するか」が治療成功の伴であると、私は考えています。
インプラントは決して「簡単な治療」ではありませんが、正しい知識と確かな技術によって、長く快適に使っていただける治療法です。不安な点やご質問があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
実際の症例を通して
治療の流れをご説明します
CASE

40代女性
左上が腫れてる。
他院で歯根破折の診断。経過観察していたが、根本的な治療を希望されたため、抜歯即時インプラントを計画。全身疾患なし。
周囲の骨を傷つけないように慎重に抜歯。抜歯窩の炎症を除去。
抜歯窩に流されないように特殊なバーにてドリリング。 洞底骨の皮質骨に固定を求めるように僅かに穿孔させる。
想定していた位置にインプラントを埋入。十分な初期トルク、ISQ獲得のため仮歯の制作、セット。
| 術後2週 | 疼痛、腫脹なし。術直後から大きな症状はなかったとのこと その後1週間ごとに消毒、歯ブラシで来院してもらう |
|---|---|
| 術後6週 | ISQ再度測定 |
| 術後8週 | 印象最特 |
| 術後10週 | 最終補綴セット |
骨の量が足りない場合


インプラントを埋め込む顎の骨の厚みや高さが足りない場合、インプラントが十分に固定されなかったり、インプラントの一部が露出してしまったりすることから治療が困難とされてきました。しかし、骨の移植や骨造成の研究開発が進み、さまざまな手法が確立されています。CTによる精密な画像診断技術も進んだことから、難症例といわれる骨量の少ない患者さまに最適な治療法をご提案し、インプラント治療を成功させることができるようになりました。
骨造成とは自家骨(自分の骨)を板状にして骨の足りない部分にネジでとめて骨の厚みを増す方法や、自家骨を粉砕して細かくしたものを骨の量の足りない部分に付け足して、人工の膜で覆って骨を造る方法などがあります。いずれにしても骨が造られるまで数ヵ月から半年の期間を要します。
また、自家骨移植の場合、下顎の先端や親知らずの付近、あるいは腸骨からブロック状に採取しなければならず、新たな外科手術が必要なため、患者さまの身体的負担が大きくなります。治療期間が延び、追加費用もかかります。
サージカルガイド


「サージカルガイド」とは、事前の治療計画の時点で集められた情報をもとに作成された、インプラントを埋入する際に用いるレジン性のガイドのことであり、「サージカルテンプレート」とも呼ばれます。実際に手術を行う時に、角度、深度、位置といった要素を事前の想定通りに再現する手助けとなり、手術のサポートや、エラー・リスクの低減を可能とします。
作製の手順としては、事前にCTスキャンを行って採取した歯型のCT画像や3Dデータをもとに、インプラント手術のシミュレーションをコンピューターで行います。そこで、インプラント体のサイズや、インプラント埋入を行う位置・角度などの要素を策定し、それらのデータをもとに、3Dプリンターによってサージカルガイドを作成します。 手術時には完成した装置を実際に用いたうえで、ガイドに沿った施術を行っていきます。
サージカルガイドを使用する利点は、インプラントの埋入がより正確に行えるという点です。また、手術前にシミュレーションを済ませることができる都合上、医師が手術中に考えることや不確定要素も減らすことができるため、手術時間の短縮にもつながってきます。さらに、インプラント埋入時のリスクを極力避けることが可能になるため、手術で切開する歯ぐきの範囲を極力小さくしたり、口内の神経や血管を傷つける可能性を下げたり、細菌感染の可能性を減らすこともできます。さらに、サージカルガイドによって理想に近い埋入が可能となるため、術後の痛みや腫れを軽減したり、インプラントをより長持ちさせたりといった、手術後におけるメリットも複数存在しています。
インプラント治療の流れ FLOW
インプラント周囲炎

インプラント周囲炎とは、インプラントの周囲組織で炎症が起こる疾患で、歯周病と同じような状態になることです。インプラント治療後、歯磨きや、歯科医によるメインテナンスが不十分になると細菌が歯肉とインプラントの境目に侵入してきます。
初期段階では、インプラント周囲の歯肉から出血がみられます。そのまま悪化すると、膿んできたり腫れたりしてきます。この状態になると、インプラントを支えていた骨が無くなっていることが多いです。重篤なケースだと、歯ぐきも痩せてしまい、インプラントを固定しつづけることが出来なくなります。インプラントの初期段階の炎症は、歯周病と同じく、自覚症状(痛み)はほとんどありません。天然の歯の歯周病治療とは違い、インプラントが細菌に感染してしまうと完治することが非常に難しいのが現状です。
インプラント周囲炎の症状
インプラント周囲炎は以下の症状を伴いますが、歯周病と同様に、明らかな痛みを伴わない場合も多く、自覚しにくいのが特徴です。
-

インプラント周囲の
歯肉の腫れや出血インプラント周囲の炎症によって、歯肉が赤みを帯び、腫れが生じます。また、歯磨きの際に歯肉から出血することもあります。
-

インプラント周囲の歯肉が退縮
インプラント周囲の歯肉や歯槽骨の破壊が始まると、歯肉が下がります(退縮)。進行すると、歯の根元部分が露出し、歯が長く見えるようになります。本来は歯ぐきの下に隠れているインプラントとの接合部やインプラント自体が露出し見えてくる場合もあります。
-

インプラントのぐらつき
インプラント周囲の歯槽骨の破壊が進むと、インプラントが骨に固定されない状態になります。わずかなぐらつきから始まり、徐々に歯の揺れが強くなり、抜け落ちてしまうこともあります。
-
インプラント周囲の
ポケットの形成ポケットとはインプラント周囲の歯肉から歯槽骨までの距離が通常より深くなっている状態を指します。歯肉の腫れが進むと、インプラントの上部 (歯の部分)やアバットメント(インプラント体と歯の接合部)と歯肉の境目に隙間ができはじめます。その中に食べかすや細菌などが繁殖し、炎症が深部へと広がって歯槽骨が破壊されます。
-
インプラント埋入周囲からの排膿
インプラント周囲にポケットが形成され、その歯肉の深い部分、骨が破壊された部分に細菌が感染して炎症が進むと、膿が出てくるようになります。いわゆる排膿が見られるようになります。
インプラントQ&A
-
通常、インプラント治療には健康保険が適用できないため、患者さんが全額負担となる自費診療となり、治療費は入れ歯やブリッジの場合と比べて高額になります。 しかし、インプラント治療に健康保険が適用されるケースもあります。例えば、外傷や腫瘍等の病気で顎骨を最近失った場合、その部位に骨移植を行って再建した場合、先天的に歯や顎骨を欠損している場合です。治療前の検査、インプラントを埋め込む手術、義歯による治療を含めて、治療が全て終了するまでに必要な治療費をよく確認してから治療を受けるようにしてください。
-
治療を開始から治療終了までに必要な期間は、患者様の状態によって異なります。顎の骨にインプラントを埋めてからインプラントに骨が結合するまでに一定の期間が必要であり、さらに、インプラントを埋めた部位の骨の状態によって結合するまでの期間に差があります。 また、インプラント治療部位の骨の造成が必要な骨量が少ない患者様の場合には、さらに治療期間が延びることになります。 インプラント治療を受ける前に、治療期間についても、しっかりと確認してから治療を受けるようにしてください。
-
インプラント埋入手術後、インプラント部が多少は腫れます。腫れる程度は状況によって異なりますが、次第に腫れは引きますのでご安心ください。 また手術部位に関連して内出血が起きることがあります。これも心配はいりませんが、不安な場合は治療前に歯科医にご質問ください。